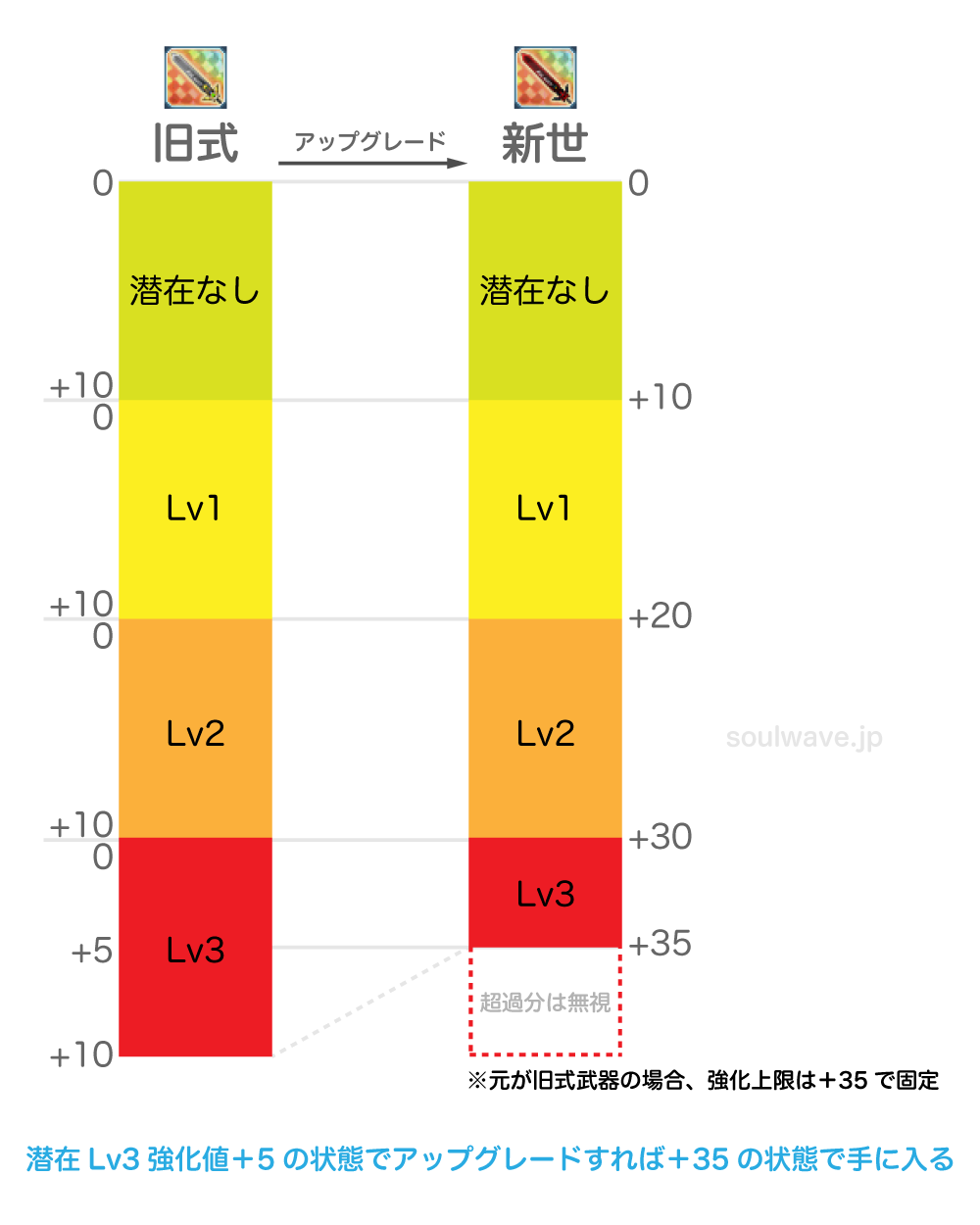スタークォーツは目を覚ます。体を横たえているのはる駐車場の路面ではなく、清潔な白いマットレスの上だ。嗅覚センサーはかすかに消毒液の匂いをスタークォーツの脳へ伝えている。視線を動かすと、自分がいるのは病院の個室だということがわかる。その証拠に、患者の状態をモニタリングすると思わしき機器が、スタークォーツの首筋とケーブルで接続されている。
窓側に人の気配を感じる。そこにはハトミがいて、花瓶の花を新しいものへと取り替えている最中だった。
スタークォーツが目覚めたのに気づいたハトミが安堵した表情を見せる。
「よかった。目を覚ましたのですね。もう三日も眠ったままだったのですよ」
「心配をかけました」
スタークォーツは体を起こそうとする。その時、ヴィーラスに切断された腕が元通りになっていることに気がつく。
「腕が治っています。それにこの感覚、ボディがまるごと新しくなっている?」
あの戦いで使った【イル・ゾンデ:嵐の型】の反動で、ボディ全体が損傷しているはずだが、制御プログラムが伝えてくるステータスはオールグリーン。つまりはキャストとして健康な状態であることを示している。
「ええ。あなたが倒れた後、すぐに新しいボディを手配しました。労災として認定されたので、費用はアークスが全額支払うので安心してください」
スタークォーツはキャスト用の健康保険に入っていたが、それでもボディを丸ごと交換するのはかなりの出費となるので、支払わずにすむのはありがたかった。自宅の購入と改装で、今は貯蓄がほとんど無いからだ。
ハトミの手腕には改めて驚かされる。ヴィーラスとの戦いは任務外の出来事であり、普通ならば労災にはならない。それを労災として費用をアークス持ちにさせたと言うことは、ハトミは単に手際が良いだけでなく、かなりの交渉力を持っていると言うことだ。スタークォーツは自分のパートナーを改めて頼もしく思った。
「こんなにも良くしてもらって、本当に助かります」
スタークォーツは心から礼を言った。
「いえ、礼には及びません。おそらく、ヴィーラスという男はすぐにでも再び現れるでしょう。パートナーが万全の状態で戦えるようにするのが私の役目です」
「それでも、ここまでのことはそう簡単にできることではありません。尊敬しますよ」
安全な場所で指示を出すだけと、管制官を軽んじるアークスの戦闘員は多い。だがスタークォーツは違った。ハトミは剣一筋に生きてきた自分にはできない仕事をやってのける。自らの役目を果たすために最善を尽くす人は、その仕事の内容にかかわらず敬意を持つべきだとスタークォーツは考えている。
「そう言ってもらえると、働いた甲斐がありました」
少しはにかみながらハトミは笑みを浮かべた。
「それで、ヴィーラスについてはどうされますか?」
ハトミが表情を引き締めながら言う。いつまでも和やかな空気のままではいられない。二人はヴィーラスについての対策を話し合う。
「当然、倒します」
スタークォーツは断言する。
「失礼ですが、彼とはどのような関係で?」
「アマサギ流の同門です。ですが、技と心を同一に鍛え、他者とともに成長することを良しとするアマサギ流において、あの男は剣術の暴力としての側面ばかり追い求め、他者をないがしろにしてきました。そのため、師範から破門されたのです。そして、ヴィーラスが破門されたのと同じ日に私が免許を皆伝されました。自尊心が高いあの男は、その事をきっかけに私を恨むようになり、数日後にヴィーラスは街のごろつきを雇って闇討ちを仕掛けてきましたが、私はそれを返り討ちにしました。以来、ヴィーラスの姿は見なかったのですが……」
「あの夜に再び現れたと言うことですね」
「ええ」
「率直に聞きます。次に戦ったとき、スタークォーツさんはヴィーラスに勝てますか?」
「正直言って、難しいでしょう。剣の技はともかく、首をはねても生きているあの不死身さをどうにかしなければ、私は負けてしまいます」
一人の剣士として認めがたいことであったが、スタークォーツは現実から目をそらさなかった。かといって、ヴィーラスを倒すことをあきらめたわけではない。現実をしっかり見つめることで、いままで気づかなかった勝機を見つけるかもしれない。
「あの不死身さは、ヴィーラスが持っていたどす黒い剣の力ではないかと私は考えています」
「それは私も同意見です。私は戦闘員であるスタークォーツさんほどフォトンを感知する能力はありませんけど、そんな私ですらあの剣からはおぞましい何かを感じ取れます」
「ヴィーラスを倒すには、あの剣の壊すか機能を封じる必要がありますね」
「まずはあの黒い剣の製造元を調べるのはどうでしょうか? それがわかればあの黒い剣の弱点や破壊方法がわかるかもしれません。私は情報部にコネクションを持っていますから、彼らに調査を依頼しようと思います」
お願いしますとスタークォーツが言おうとした時、厳格な雰囲気を持つ男の声が病室に響く
「いや、その必要はない」
腰病室に入ってくるヒューマンの男をスタークォーツは知っていた
「ハヤブサ師範。いらしていたのですか」
彼は開祖アマサギの子孫であり、またアマサギ流の現師範でもある人だ。
「おまえが入院したと聞いて見舞いに来た。しかし、思いもよらぬ話を耳にした。ヴィーラスが手にしたという黒い剣は、おそらく黒のセイバーだろう」
「あの剣をご存知なのですか?」
「そうだ」
ハヤブサは頷く。
「事の始まりは200年ほど前、ちょうど惑星ナベリウスが発見されたばかりの頃だ。当時、セイバーという新しい武器カテゴリを開発するため、いくつかのプロトタイプが作られていた。黒のセイバーはその内の一本だ。この剣はダーカーの力であるブラックフォトンを利用するという機能を持っている」
「そんな危険な研究がされていたなんて……」
「当時はまだダーカーについて未知の部分が多く、ブラックフォトンの危険性は深く理解されていなかった。それ故に、黒のセイバーを手にしたテストユーザーであるカラスという男はブラックフォトンに精神を支配され暴走してしまったのだ。今のヴィーラスのようにな」
「当時、その事件に対してどのような対処がされたのですか」
黒のセイバーに対する勝機がそこにあるかもしれないとスタークォーツは考えた。
「プロトタイプの中にはもう一本、白のセイバーと呼ばれるものがあった。それにはブラックフォトンの力を弱体化させる特殊なテクニックを発動させる機能を持っていた。白のセイバーのテストユーザーであった開祖アマサギはその力を使って黒のセイバーに支配されたカラスを倒したという」
「黒のセイバーはその時、破壊されなかったのですか?」
「無論、開祖は黒のセイバーを破壊されようとした。しかし、かの剣は開祖の前から逃げたのだ」
「逃げた?」
「開祖によれば、最初の使い手であるカラスの精神に影響を受け、黒のセイバーは知性に目覚めたという。黒のセイバーは倒されたカラスの死体を操り、アマサギの前から姿をくらました。その後、ヴィーラスはどこかで黒のセイバーを手に入れたのだろう。開祖の血を引くものとして、この事態は見過ごせない。ヴィーラスと黒のセイバーは私が倒す」
「待ってくださいハヤブサ師範。その役目、どうか私に任せていただけないでしょうか」
「しかし、スタークォーツよ。おまえは黒のセイバーとは無関係だ。巻き込まれただけの者に自らの使命を押し付けるわけには……」
「黒のセイバーと無関係でも、ヴィーラスとは無関係ではありません。私があの男を見逃していなければこのよう状況にはならなかったはずです」
あの日、ヴィーラスに情けをかけるべきではなかったと、スタークォーツは過去を悔やんでいた。
破門された逆恨みをぶつけるため、自分で雇った数人のゴロツキとともに現れたヴィーラスを、スタークォーツは返り討ちにした。
スタークォーツとヴィーラスは同じ日にアマサギ流の門を叩き、同じ年月を修練に費やした。しかし、自らの可能性の極地を目指す者と、ただ弱者をいたぶる手段を求めた者とでは、その身に宿る力は歴然であった。ヴィーラスの剣はスタークォーツに一太刀浴びせるどころか、髪の毛一本斬ることすら叶わなかった。
持っていた剣をスタークォーツに弾き飛ばされたヴィーラスは、額を地面に擦り付けながら「見逃してくれ」と言った。それはただの命乞いであった。自らの悪行を認め、それを恥じ、罪を許して欲しいという気持ちはひとかけらもない。道徳も因果への応報も、その一切を無視し、ただひたすらに助かりたいという浅ましい自己保身の表れであった。
そのあまりにも卑しい姿に対し、スタークォーツは軽蔑よりも憐れみの気持ちほうが強かった。この男に人なみの良心があれば、暴力の魅力に心を支配さていたとしても、必ず何処かで過ちに気付き、ここまで情けない姿を晒すこともなかったはずだ。
自尊心を自ら手放したヴィーラスはもはや精神的に再起不能となっているだろう。スタークォーツはこの男に罰を与えようとする気持ちはなくなっていた。自分の剣をこんな男の血で汚すこと自体に強い嫌悪感すらあった。だから「何処にでも消えなさい」と見逃したのだ。
しかし、こうして黒のセイバーによって人ならざる怪物となって帰ってきたことを考えると、あの日は世界の果てまで追い詰めてでもヴィーラスを殺すべきであった。
「お願いです、ハヤブサ師範」
スタークォーツはベッドから出て、師匠の前に立つ。その両目は機械仕掛けとは言えど、確かな意思が宿っていた。
「分かった。意思は固いようだな」
「ありがとうございます」
スタークォーツは頭を下げて感謝の気持ちを伝える。
「ただし、条件がある。黒のセイバーを倒すには我が家に伝わる白のセイバーが必要となるが、お前には白のセイバーの使い手に相応しいか試練を受けてもらう」
「望むところです」
スタークォーツは躊躇なく言った。
「試練は私の道場で行う。付いてこい」
「はい」
それから退院手続きを済ませて、スタークォーツは師匠と共に道場へ向かう。その際、ハトミは別行動をすることになった。
「スタークォーツさんが試練を受けている間に、私はヴィーラスの行方を追いましょう。居場所が分かったらすぐに連絡します」
「お願いします。ハトミさん」
白のセイバーとして認められたとしても、ヴィーラスが何処にいるかわからなければ意味がない。彼女ならば必ず見つけ出してくれるだろうと、スタークォーツはハトミを見送った。
オラクル船団の建物は、主に鉄骨、コンクリート、高強度の合成樹脂などで建設されているが、アマサギ流の道場は木材によって作られている。
数百年前の時代は植物は大気中のフォトンを吸収していると考えられており、よりフォトンが身近となる生活をするために木製の建築物が数多く作られた。しかし、現在はその説は間違っていると証明されており、剛性の高い建材で建物が作られるようになった。
現在では新たに木造建築物が作られることはなく、過去に建てられたものは文化保護の名目で状態維持されている。アマサギ流の道場はそんな木造建築の一つだ。
道場に到着すると、ハヤブサは建物の中には入らず、裏手の方へと向かっていった。
「ハヤブサ師範、試練は道場で行わないのですか?」
「ああ。白のセイバーの試練は別の場所で行う」
道場の裏手にはアマサギ流の開祖であるアマサギの墓があった。師匠は香を焚くための受け皿を時計回りに回転させると、墓が重い音を立てながら後ろへとスライドしていく。
「こんなところに階段が……」
スタークォーツの目の前には地下へと続く入り口が姿を見せていた。
師匠とともに階段を降りていく。かなり長い。おそらく5階分以上は下っている。
階段が終わった先は闇であったが、二人が一歩足を踏み入れると、対人センサーが感知したのか照明が自動的につく。その場所は一辺が10メートルほどの完全な正方形となっている空間だった。
中央には剣が台座の上に安置されていた。はっと目がさめるほどに白く美しい刃を持つ剣だ。おぞましい黒のセイバーとはあらゆる意味で真逆の印象を感じ取ったスタークォーツは、あれこそが白のセイバーだと理解する。
「あなたが門下生をここに連れてくるなんて、何かありましたか?」
どこからともなく、女性の声が聞こえてくる。
「破門したかつての門下生に黒のセイバーが取り憑きました。かの邪剣を倒すため、このスタークォーツが白のセイバーに相応しい剣士か、どうか貴女自身の手で確かめていただけないでしょうか?」
師匠が女性の声に対して答える。
白のセイバーの近くでフォトンエネルギーの光が生じる。光は人の形を取り、女性の姿へと変質した。
「これは、ソリッドホログラム?」
スタークォーツが目の前の現象の名を口にする。それはフォトンを利用した実体を持つホログラムで、アークスでは主に模擬戦のエネミーを生成するのに利用されている技術だ。
「この御方こそ、我が流派の開祖であるアマサギだ。彼女は自身の人格をコンピュータに保存し、その魂は今も生きていらっしゃる」
師匠が目の前の女性の名を告げる。
「これは私のわがままに過ぎません」
アマサギは恥じらいながら言った。
「自分の代で黒のセイバーを見つけ出せなかった私は、白のセイバーを次の世代に託すしかありませんでした。しかし、託す相手が相応しい者かどうかは、どうしても自分の手で確かめたかったのです。キャストになれば何百年も生きることは出来ますが、病弱でもなければ肉体の欠損もない私にキャスト化手術の許可は降りませんでした。ゆえに、こうした形で浅ましく生き続けていたのです」
アマサギは台座の上にある白のセイバーを取る。
「さあ剣を抜きなさい、スタークォーツ。貴女が白のセイバーに相応しい者かどうか、この私に自らの技を持って示すのです」
凛としつつも太陽のように熱い闘志がアマサギから放たれる。
「わかりました」
スタークォーツは鞘から剣を抜く。
自らの流派の開祖自身と刃を交える。強い緊張が全身を駆け巡るのをスタークォーツは感じていたが、同時に喜びもあった。ただ独りで剣を振るっているだけでは剣の道は開かれない。強い剣士と全てを振り絞った戦いの果てに、目指すべき極地は存在するのだ。
アマサギは白のセイバーを肩に担ぐような構えを取る。
対してスタークォーツは剣の先端を相手に向け、片手を刃に添える構えを取った
「いざ尋常に」
「勝負!」
スタークォーツとアマサギ。二人の剣士がぶつかりあう。